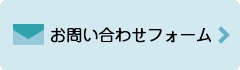帯状疱疹について
更新日:2025年11月19日
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)のウイルスが原因で起こる痛みをともなう皮膚の病気です。水痘にかかったことがある方なら、誰でもかかる可能性があります。水痘は、治った後もそのウイルスが体内に潜伏し、加齢や疲労、ストレス等で免疫力が低下した時に、再び活性化し、「帯状疱疹」として発症します。
加齢などによる免疫力の低下の影響もあり、50歳以上から発症率が高くなり、80歳までには、約3人に1人がかかると言われています。
症状について
初期症状は、皮膚の痛みで体の左右どちらか片側の神経に沿って起こります。数日後にはピリピリ感・痛みのある部位に発疹が現れます。発疹は徐々に広がっていき、やがて水疱(水ぶくれ)に変化します。水ぶくれは時間の経過で破れてかさぶたとなり治癒します。皮膚の症状が元に戻るまでには1か月程を要します。また、合併症を伴うことがあり、代表的なものとして、皮膚の症状が治まった後も3か月以上痛みが続く「帯状疱疹後神経痛(PHN)」があります。
治療について
帯状疱疹は、症状がひどくなる前に受診し、治療を始めることが重要です。抗ウイルス薬を投与することにより、痛みの期間の短縮、発疹の発生の抑制、皮膚の症状の治癒を促す効果が得られますが、十分な治癒効果を得るためには、発症後速やか(発疹が現れてから3日以内)に投与を開始することが望ましいとされています。また、痛みを和らげる鎮痛薬等が使われる場合もあります。
帯状疱疹を疑う症状が現れた際には、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。
予防について
免疫の低下が帯状疱疹につながることから、日頃からの体調管理に気をつけ、できるだけ健康的な生活習慣を保ち、免疫力を高めることが大切です。バランスのとれた食事や、適度な運動、適切な睡眠を心掛けましょう。50歳以上の方については、帯状疱疹予防ワクチンを接種することも有効であるとされています。
帯状疱疹の予防接種について
令和7年度から、帯状疱疹の予防接種が定期化されました。対象者
1.令和7年度中に、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳以上になる方(令和12年度からは、65歳の方のみ対象となります。)
2.接種時点の年齢が60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
対象者には、5月下旬に予診票を送付しました。予診票が届かない方、紛失や転入により予診票がない場合は、お問い合わせください。
原則、過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了している方は、定期接種の対象外となります。
(ワクチンの効果や既往歴等から、医師が接種を行う必要があると判断し、市がそれを認めた場合は、定期接種の対象となることもあり
ます。接種をご希望の方は、事前に接種医とご相談ください。)
接種期限
令和8年3月31日接種回数・自己負担金
| ワクチン種類 | 接種数数 | 自己負担金 |
| 生ワクチン(ビケン) | 1回 | 4,000円 |
| 不活化ワクチン (シングリックス) |
2回 | 10,000円 (1回当たり) |
2回目の接種についても、令和8年3月31日までに接種しなければ、定期接種の対象となりませんので、ご注意ください。
生活保護世帯の方は事前に申請すると無料で接種が受けられます。必ず接種前に健康推進課又は各総合支所市民福祉課で自己負担金免除証明書の交付を受けてください(生活保護受給証明書を持参の上、申請が必要です。)。渡波支所、稲井支所、荻浜支所、蛇田支所での申請はできません。接種後の申請はできませんのでご注意ください。
接種場場所
石巻市、東松島市、女川町の指定医療機関令和7年度帯状疱疹予防接種実施医療機関
指定医療機関以外で接種を希望される方
上記対象者で、指定医療機関以外で予防接種を受ける場合、接種日の10日以上前に「予防接種実施依頼書」の交付申請が必要です。
手続き等に関しては事前に健康推進課へお問い合わせください。
詳しくは「市外の医療機関で予防接種を希望する場合」をご覧ください。
申込み等
- 接種を希望する方は、指定医療機関に直接予約してください。
- 対象者となる方には予診票を郵送しますので、説明書をよく読み理解した上で記入してください。
令和7年度は5月下旬に送付しました。予診票が届かない方、紛失や転入により予診票がない場合は、お問い合わせください。 - 接種の可否は、医師が予診票を確認し、診察した上で決定されます。
- 医療機関から交付される接種済証は大切に保管してください。
紛失や転入で予診票をお持ちでない場合は再発行を行います。下記へお問い合わせください。
予防接種の効果や注意事項など、詳しくは「令和7年度帯状疱疹予防接種の説明書」をご覧ください。
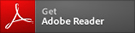 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111
予防接種・健診担当
地域医療・総務担当
歯科保健担当
母子保健(乳幼児健診)担当
精神保健担当
成人保健担当
栄養担当