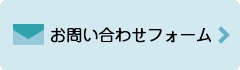令和7年度施政方針
はじめに
令和7年「石巻市議会第1回定例会」に「令和7年度各種会計予算並びに諸案件」を提案するに当たり、市政運営に取り組む所信の一端と施策の大綱について御説明申し上げます。
世界を見ますと、地球規模での異常気象、長期化している紛争、更には日本の友好国におきましても政情が流動化していたり、関税問題が取り沙汰されており、エネルギー価格や穀物・食料価格の高止まりなども懸念されます。
一方、国内を見ますと、いわゆる「団塊の世代」が全て75歳以上の後期高齢者となる年でもあり、人口減少・少子高齢化という構造的な課題は一層厳しい環境を迎えます。
また、生成AI、DX(デジタルトランスフォーメーション)、GX(グリーントランスフォーメーション)など、100年・200年に一度という産業構造の大転換期の最中にあります。
そうした中、地域経済は個人消費や雇用などを中心に、緩やかに回復しつつありますが、地域が直面している複雑化・多様化している諸課題に対応していくことは、なかなか容易なことではありません。
このような状況下で、本市の「第2次総合計画前期基本計画」は順調に進捗しており、最終年度を迎えることとなります。総力を挙げて市民の皆様の評価に応える成果を達成してまいります。
なお、今日、少子化や人口減少が進む中にあって、財政問題は環境問題と同様、世代間倫理に関わる課題でもあります。その衡平を確保するためには、まだ生まれていない世代も含む将来世代の視点に立って、現時点において何が必要かを議論し、実践することが重要であり、市議会議員の皆様や市民の皆様と議論してまいりたいと考えております。
さて、私が市長に就任してから間もなく4年を迎え、任期も残すところあと僅かとなりました。この間、市議会議員各位をはじめ、市民の皆様の御支援、御理解をいただきながら、「全ての市民が住むことに誇りを持てるまちづくり」の実現に向け、常に現場主義を貫き、動く市長室等をはじめ、市民の皆様との対話を通じて各地域の課題を把握し、その解決に向け「オール市民」で取り組んでまいりました。
公約に掲げた51の項目につきましては、その全てに着手し、「子ども医療費助成対象者拡大」など、23項目が目的を達成できたものと考えております。残る28項目につきましても、概ね順調に進んでおり、全ての項目について、一定の成果を残すことができたものと考えております。
最大の目標でありました東日本大震災からの復旧・復興に当たっては、国内外より励ましのメッセージと御支援を賜り、私たち市民にとって、再び平穏な生活を取り戻すための一歩を踏み出す力となり、心の支えとなりましたことに、改めて感謝申し上げます。
一方で、心の復興はもとより地域コミュニティの再構築などのソフト事業には、今後も継続して取り組んでまいります。
昨年の元日に発生した能登半島沖を震源とする巨大地震とその被災地を襲った9月の豪雨により、多くの尊い命が奪われました。亡くなられた方々に哀悼の誠を捧げるとともに、被災された方々に心より御見舞いを申し上げます。
本市は、東日本大震災において、物心両面にわたり多大な御支援をいただいておりましたことから、発災直後、先んじて物資・人的支援をはじめ、震災による経験を踏まえた様々な対応を迅速に行ってまいりました。
また、被災地の皆様が一日も早く日常を取り戻せるよう、被災自治体の事務負担を軽減し、災害対応に注力していただくため、石川県珠洲市、輪島市、志賀町に対し、ふるさと納税の「代理寄附」を行いました。現在も被災された方々に心を寄せ、職員派遣等を通じて継続的に支援をさせていただいており、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
本年は、平成17年の1市6町による合併から、20年目の節目を迎えます。これまで、各地域が持つ歴史や風土・文化、多種多様な魅力を活かしながら、地域における一体感の醸成と住民同士の絆を育むことを念頭に、様々な施策に取り組んでまいりました。
一方で、なお取り組むべき課題もありますことから、引き続き、各地域のポテンシャル、そして魅力を内外に発信し、特色ある発展を目指してまいります。
令和6年度を振り返りますと、市民の皆様の長年の悲願でありました都市計画道路「七窪蛇田線」が、3月に全線開通いたしました。石巻駅西側の線路によって通行が遮断されていた山下地区と中里地区とを結ぶ高架橋の整備により、渋滞緩和はもちろんのこと、災害時における市民の迅速かつ安全な避難が可能となったほか、物流機能が向上したことで、産業振興や地域経済の活性化も期待されております。
また、狭あいな幹線道路に加え、最寄りの救急医療機関までの移動に時間を要する雄勝地区半島部において、夜間の離着陸が可能なヘリポートが、本年4月には供用開始を予定しております。
将来を担う児童生徒に対する教育は、社会の発展と地域の未来を支える重要な基盤となります。特に本を読む習慣は知識の習得にとどまらず、想像力や表現力を豊かにし、将来を生き抜くための土台になることから、市内全ての小学校に電子書籍を導入し、児童が自主的に、いつでも、どこでも、好きなだけ本を読むことができる環境を整備いたしました。
また、市内全ての小中学校へ導入を進めている校務支援システムが本年4月に稼働することで、児童生徒の出欠状況や教員の出退勤等の一元管理が図られ、効率的な校務処理体制が整い、学校現場における業務負担の軽減及び教育への効果も期待されております。
石巻市博物館では、常設展に加え企画展を2回、特別展を1回開催し、また、5月には、本市博物館を核とした文化芸術振興に関する連携協力協定を武蔵野美術大学と締結し、市内の中高生と武蔵野美術大学の教員・学生が、フィールドワークやワークショップに、大学の授業方法も取り入れながら絵画制作に取り組みました。その成果は、石巻市博物館と武蔵野美術大学により「森と海の美術展」を開催し、発表するとともに、開館3周年を迎えた11月には、「彫刻家 高橋英吉に関する記念イベント」を実施するなど、本市博物館活動を大いに盛り上げ、その魅力を内外に発信することができました。
また、約2年ぶりにリニューアルオープンいたしましたサン・ファン館は、大型グラフィックや音声・映像を用いた分かりやすく魅力的な展示内容となり、二次元コードを活用するなど、インバウンドへの対応も強化されたほか、4分の1スケールの復元船については、AR技術を用いてスマートフォンやタブレットで解説するなど、楽しみながら歴史を学べる施設へと生まれ変わりました。サン・ファンパークで開催されたオープン記念イベントでは、キッチンカーや石巻観光協会と連携した観光関連団体による交流物産展が多くの来場者で賑わい、本市観光分野の新たな魅力として注目を集めるなど、観光交流人口の更なる拡大が期待されております。
東日本大震災発生の日から5000日となった11月16日、石巻南浜津波復興祈念公園内の「がんばろう!石巻」看板前で、市民有志の皆様によって、犠牲者を追悼する明かりがともされました。復興ハード事業の完結もあって、震災の爪痕を目にすることも難しくなっている中、私は、東日本大震災最大の被災地である本市が、震災の記憶と教訓をいかに未来へとつないでいくべきかとの思いを強くし、関係団体等と連携を図りながら、本市の2つの震災遺構も活用し、震災伝承に取り組んでまいりました。
これらの枢要な政策を実現、推進していくためには、財源の確保も重要でありますので、ふるさと納税の収入増加に向けて、あらゆる機会を捉え、自ら先頭に立って積極的にPRしてまいりました。多様なニーズに対応するための魅力的な返礼品の追加に向けた企業訪問や事業者向けの研修会等の開催をはじめ、各種ポータルサイト内のPR広告における宣伝効果の検証、分析、改善などに取り組んだ結果、昨年12月末現在において、寄附件数が約11万7千件、寄附金額は約18億1千万円に達し、寄附金額は対前年度同期比で約1.5倍となりました。本市の魅力をより多くの方々に知っていただくとともに、寄附金額については定住支援や結婚等支援事業をはじめ、母子保健、子ども・子育て支援事業などに充当し、併せて返礼品による地域経済効果も高めるなど、極めて効果的な促進ができたものと考えております。
さて、日本経済はコロナ禍からは回復基調にあるものの、世界情勢の不透明感や自然災害などによる物価高騰が続き、市民生活や事業活動への負担が増す一方で、賃金の上昇は十分とは言えず、実質所得の低迷が懸念されております。
国においては、所得税の課税最低限、いわゆる「年収の壁」の引き上げにより、手取りを増やすための構造的賃上げに向けた環境整備や少子高齢化に伴う労働力不足に対応するため、働く意欲のある高齢者や女性などの就労を促進し、誰もが年齢や性別にかかわらず能力や個性を最大限発揮できる社会を目指すとともに、生産性向上につながる成長分野への投資促進のほか、更なる地方創生の推進などの政策を重視する方針を示しております。
国が、地方創生の本格的な取組を開始してからの10年間を総括し、新たに示した「地方創生2.0」の基本的な考え方を踏まえ、本市が抱える諸課題に向き合いつつ、これまでの施策の検証を行い、まずは、結婚や子どもを持ちたいとの希望が叶い、仕事と子育てや介護の両立が可能となる柔軟な働き方の実現に向けた支援を継続するとともに、国が進める地方創生事業等も踏まえ、「稼ぐ力の強化・創出」や「将来世代の育成」など、5年先、10年先を見据えた種まきをしっかりと進めてまいります。
また、社会保障経費や復興事業で新たに整備した公共施設の維持管理経費の増加や老朽化対策など、より厳しさを増している財政状況を踏まえ、人口減少社会を見据えた健全な財政運営に努めるとともに、100年・200年に一度と言われる経済・社会基盤の転換期を踏まえたDXの推進が急務となっていることから、その活用により、市民サービスの利便性向上につなげていくなど、将来を見据えた持続可能な市政運営に取り組んでまいります。
重点施策
それでは、令和7年度に取り組む6つの重点施策について、述べさせていただきます。
1.全ての世代が生きがいを持って活躍できるまちづくり
一つ目は、「全ての世代が生きがいを持って活躍できるまちづくり」についてであります。
地域が活気に満ちあふれるためには、その地域の人々が生き生きと生活できることが基本です。多彩な祭りや文化、スポーツ、趣味などの活動を通じて楽しく暮らし、石巻への誇りや愛着を深められるよう、次の各施策に取り組んでまいります。
まず、「交流人口の拡大」に向けた取組といたしましては、本市最大のイベント、石巻川開き祭りをはじめ、サマーフェスタ・イン・かほく、おがつ海鮮まつり、かなんまつり、ものうふれあい祭、北上にっこりまつり、牡鹿鯨まつりなど、各地域の歴史や文化と四季折々の豊かな自然が融合した魅力ある祭りやイベント等の開催により、観光誘客を推進してまいります。
また、プロアスリートやパラリンピアンによるスポーツ教室やプロスポーツチームと連携した交流イベント等のほか、国内でも屈指の人気を誇るサイクルイベントとして定着しているツール・ド・東北やいしのまき復興マラソンなどを引き続き開催してまいります。
さらに、いしのまきスポーツコミッションが主催する各種大会・イベントやスポーツ合宿の誘致、地元競技団体による大会運営の支援に加え、武道ツーリズムの商品開発などについて、引き続き連携して進めてまいります。
併せて、スポーツ全体の向上と市民の健康増進に寄与することを基本理念に、子どもから高齢者、障がいのある方まで、全ての市民が気軽に利用できる場を目指し、第3種公認の「石巻市総合運動公園陸上競技場整備事業」を推進してまいります。
文化芸術は、感動や共感によって心に潤いをもたらし、心豊かな人生を送る上で欠かせない役割を担うとともに、市民の郷土愛や誇りの醸成に大きく寄与することから、文化芸術の振興を総合的に推進していくため、第2次石巻市文化芸術基本方針に掲げる施策の展開をはじめ、生涯学習を総合的に推進しながら「第3次石巻市生涯学習推進計画」の策定を進めてまいります。
また、石巻市博物館では、本市の歴史・文化を学術的な視点で分かりやすく紹介し、市民の知的好奇心を満たす機会を提供することで、本市の更なる魅力向上を図り、時宜にかなった企画展・特別展を引き続き開催するとともに、武蔵野美術大学との連携・協力を通じ、博物館を核としながら文化芸術を振興してまいります。
さらに、令和5年11月、マルホンまきあーとテラス大ホールにおいて、市民合唱団による「復活の第九」が12年ぶりに披露され、歌う人と観客とが一体となり、来場した多くの方々が感動を分かち合いました。東日本大震災最大の被災地である本市が、東北の更なる復興、発展のリーダーとなるべく、「芸術文化支援事業」として、歌える喜び、聴ける喜びを共に感じ、音楽の力で被災者を含む全ての人々に勇気と希望を与える「石巻第九」を歌い継ぐイベントの開催を支援してまいります。
次に、「高齢者の生きがいづくり」に向けた取組といたしましては、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康的な日常生活を送ることができるよう、各種介護予防事業を実施し、心身機能の低下を防ぐ取組を進めるほか、コロナ禍前の状況を取り戻すため、地域住民同士が交流し、新たな仲間をつくる機会を提供するとともに、高齢者の知識や経験を活かした創造的な活動や趣味活動の場も充実させてまいります。
次に、「豊かな自然の保護と魅力の発信」に向けた取組といたしましては、本市の健全で恵み豊かな環境を保全し、美しいふるさとを次の世代に継承するため、「環境基本計画」の策定を着実に進め、市民・事業者と行政とが連携して、2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す、「ゼロカーボンシティ・石巻」の実現に向けた取組を進めてまいります。
また、家庭から排出されるごみの削減を図り、リサイクル率を向上させるため、プラスチック類の再資源化に向けた収集・処理体制の構築も引き続き進めてまいります。
次に、「SDGsの推進」に向けた取組といたしましては、一人ひとりの関心や意識向上を図るため、今後も市内の学校への出前講座のほか、企業等による取組の紹介やワークショップなど、普及啓発活動を積極的に推進し、SDGsの市民認知度、取組度の更なる向上を目指してまいります。
2.安全・安心なまちづくり
二つ目は、「安全・安心なまちづくり」についてであります。
気候変動による海面水温の上昇によって、風水害の頻発、激甚化が懸念されるとともに、初の南海トラフ地震臨時情報の発表を踏まえ、自然災害に対する一層の防災意識の向上や対策に取り組む必要があります。
また、全ての市民の生命と財産を守る基盤として、医療体制の強化を図るとともに、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、安全・安心なまちづくりに向け、次の各施策を進めてまいります。
まず、「災害に強いまちづくりの確立」に向けた取組といたしましては、「津波避難対策緊急事業」として、宮城県が公表した「津波浸水想定」や「石巻市地域防災計画」の改訂内容を踏まえ、「津波避難対策緊急事業計画」を策定するとともに、新たに必要な避難関連施設の整備等や防災サインの見直しなどを進め、津波避難対策の一層の強化を図り、地域防災力の向上に努めてまいります。
また、「防災行政無線更新事業」として、「防災行政無線整備基本計画」に基づき、防災行政無線の屋外子局及び戸別受信機の適正配置やスマートフォンをはじめとした情報伝達手段の多重化により、災害時における防災情報の発信強化に引き続き取り組んでまいります。
さらに、「令和6年能登半島地震」において、道路の寸断により複数の集落が孤立し、救助活動が困難を極め、改めて緊急時に備えた対策の重要性が浮き彫りとなる中、昨年11月に女川原子力発電所2号機が13年ぶりに発電を再開しました。
万が一の原子力災害時に避難を確実に行うためには、避難路の整備が不可欠であることから、住民の生命、財産を守る責務を有する国及び事業主体である県に対し、災害に強い避難機能を有する道路の早期整備を強く求めていくとともに、避難路としての機能が脆弱な寄磯浜前浜地区において、災害時の迅速な避難の確保に向けて、引き続き避難路の整備に取り組んでまいります。
近年、線状降水帯や集中豪雨が頻繁に発生しておりますことから、「緊急冠水対策事業」として、冠水常襲箇所における被害の軽減・解消に引き続き努めてまいります。
次に、「市民の健康・命を守る医療体制の充実」に向けた取組といたしましては、東日本大震災に伴う医療施設の偏在により、東部地区と西部地区の医療体制の格差が拡大し、産科医及び小児科医が不足している状況等も踏まえて創設した「医療施設開設支援事業」の周知を一層強化し、民間医療施設の開設を促進してまいります。
また、休日及び夜間における外来・入院診療、救急医療等の医療体制を確保するため、医師会や医療機関と連携するとともに、診療所の運営により、離半島部の地域住民が安心して受診できる、信頼性の高い医療の提供に引き続き取り組んでまいります。
夜間急患センターにつきましては、石巻赤十字病院との緊密な連携による機能分担を進展させ、一次救急医療の充実を図ることで地域医療に貢献し、医師派遣元との協力関係を維持しながら、安定した運営の継続に努めてまいります。
さらに、「石巻市公立病院経営強化プラン」に基づき、石巻市立病院においては、石巻赤十字病院をはじめとする二次、三次医療機関と連携を強化し、石巻圏域における切れ目のない医療の提供に努めるとともに、牡鹿病院では、地域の医療サービス体制を確保しながら、ニーズに合った医療機能の検討を進めることにより、継続的かつ安定的な医療提供体制の確保を図ってまいります。
次に、「介護従事者の働く環境整備と人材育成強化」に向けた取組といたしましては、高齢化率の上昇に伴い、介護ニーズが更に高まることが予想されるため、事業者が安定的にサービスを提供できるよう、適切な水準の介護報酬の設定を含む介護職員の処遇改善や労働環境の整備について、国に対し引き続き要望してまいります。
また、介護人材の育成強化を図るため、介護事業所が主催する、介護人材確保対策や地域住民への介護・福祉に関する意識啓発を目的としたイベントへの支援を継続するとともに、介護事業所に勤務する職員を対象とした研修会等を開催してまいります。
さらに、働く意欲のある高齢者の就労に着目し、60歳以上の方を対象とした合同企業説明会を開催し、介護事業者による人材確保の取組を継続して支援するとともに、本市への居住及び就労を条件に奨学金返還額の一部を助成する「奨学金返還支援事業」制度を周知し、地域包括ケアの推進に必要となる医療、介護、福祉分野の専門職の人材確保と定住促進を図ってまいります。
次に、「地域共生社会の実現」に向けた取組といたしましては、地域住民が主体的に地域の課題を把握し、その解決に取り組める環境整備と幅広い内容の相談を包括的に受け止める横断的な相談体制を構築していくとともに、高齢者、障害者、子ども等も対象とした通所サービスを提供する「共生型地域包括ケアサービス事業」を継続し、保健・福祉を必要とする人たちの居場所の確保と見守り等を行い、利用者相互の交流を促進し、社会的孤立の解消と心身機能の維持向上に取り組んでまいります。
また、急速に進展する少子高齢化や労働力不足が懸念されておりますが、地域医療・介護・福祉のサービス水準を維持し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするため、在宅医療・介護連携推進会議等において、各専門職による課題抽出とその対応を検討するなど、多職種間における顔の見える関係が保持できるヘルスケアネットを推進し、医療と介護の連携を強化してまいります。
被災者支援として行ってきた公営住宅等入居者への見守りや声がけについては、高齢単身世帯や特に配慮が必要な世帯など、依然として見守りを必要とする入居者が多いことを踏まえ、「公営住宅等見守り連携事業」を継続し、民生委員、地域包括支援センター、社会福祉協議会等との連携を一層強化し、孤立や孤独防止に取り組んでまいります。
3.人口減少対策と地域コミュニティの強化
三つ目は、「人口減少対策と地域コミュニティの強化」についてであります。
人口減少は、確実に進行していく深刻な問題です。労働力不足による経済活動の停滞、市場規模の縮小、そして社会保障費の増大など、その影響は地域のあらゆる面に波及することから、減少のスピードを抑制、安定化させ、地域コミュニティを維持していくため、次の各施策に取り組んでまいります。
まず、「出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支援」に向けた取組といたしましては、少子化の要因のひとつである未婚化・晩婚化に対応するため、独身男女に対し、団体等が実施する出会いの機会を提供するほか、結婚への意識向上を図る事業への支援や結婚相談会を開催してまいります。
併せて、若い世代の婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、一定の所得層の新婚世帯における賃貸住宅への入居や住宅取得等を支援する「結婚新生活支援事業」を引き続き実施してまいります。
また、昨年11月、誰もが仕事と家庭生活の調和の取れた働き方ができる地域社会を実現するため、私をはじめとする管理職員以上の職員、市議会正副議長が、職場で共に働く部下や同僚のワーク・ライフ・バランスに配慮し、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織としても成果を上げつつ、自らも仕事と私生活を楽しむ「イクボス」を目指し、この趣旨に御賛同いただいた市内企業等の皆様と共に「石巻市イクボス宣言式」を執り行いました。今後は、働きやすい職場環境づくりやワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む「石巻市イクボス宣言企業」の拡大を図り、働きやすい職場環境や子育てしやすい地域づくりを市全体で推進してまいります。
さらに、本市職員、特に男性職員の育児休業の取得を促進するため、任期付職員や会計年度任用職員を代替職員として配置し、育児休業を取得した職員及び職場双方の負担軽減を図り、育児休業を取得しやすい環境を整備することで、育児等と仕事の両立を支援してまいります。
妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支援といたしましては、「妊婦のための支援給付金給付事業」をはじめ、様々な課題を抱えている妊婦や子育て家庭の現状を把握し、子育てに関する各種事業の利用促進に努めるほか、「産後ケア事業」の県内広域利用や利用期間及び回数の拡充により、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進してまいります。
また、核家族化や共働き世帯の増加、就労形態の多様化に伴い、保育施設に求められる役割が拡大している状況を踏まえ、保護者の多様な保育ニーズに対応するため「第2期石巻市公立幼稚園・保育所・こども園再編計画」を着実に進めるとともに、「保育士宿舎借り上げ支援事業」により、民間事業者の保育士確保について引き続き支援してまいります。
地域の宝であり、市の宝である子どもたちが健やかで幸せに成長できる「こどもまんなか」社会を実現するため、「第3期石巻市こども・若者未来プラン」を着実に実行し、子どもや子育て当事者等の声を聴きながら、子どもの権利の普及啓発や安心して過ごせる居場所の充実に積極的に取り組んでまいります。
子どもや若者にとって、自らの意見を十分に聴いてもらい、自分たちの声によって社会に変化をもたらす経験は、自己肯定感や社会の一員として主体性を高めることにもつながります。本市に住み続けたいと思えるシビックプライドの醸成を図り、全ての子ども・若者が身体的・精神的・社会的に、将来にわたって幸福な状態で生活を送ることができる社会を目指し、新たに「こどもまんなか推進事業」に取り組んでまいります。
また、子育てに悩みや不安を抱える保護者とその児童に対し、健全な親子関係を形成するために必要な支援を実施することにより、子育て世帯に対する包括的な支援体制の強化を図ってまいります。
次に、「教育環境の充実」に向けた取組といたしましては、今日、生成AIを中心とするデジタル技術が加速的に進化を遂げておりますが、生成AI利用率において、我が国は後進国レベルと言われております。人間の脳と同レベルのAIの誕生については、賛否両論、諸説ありますが、「AIは、今から2、3年以内に人間とほぼ同一の知能レベルを持つようになる」とも言われており、一方で、「AIに仕事を奪われるのではない、AIを活用する人に仕事を奪われるのだ」とも言われております。かかる近未来において期待される教育は、その技術習得のためにも、そしてリスク抑制のためにも、リベラルアーツ(一般教養)の習得と言われております。したがいまして、引き続き教育環境の充実に努め、将来世代の皆さんには、その基礎をしっかりと修めていただけますよう対応してまいります。
また、本市の未来を担う幼児が、生涯にわたって学び続ける力を育むための「幼児教育推進事業」として、幼児教育アドバイザーが公立及び私立の幼稚園、保育所、こども園、小学校を巡回訪問し、幼稚園教諭や保育士への助言・指導を行うほか、小学校教諭に対する幼児期の学びを生かした授業づくりの指導により、その実態を踏まえた学びの充実を図り、全ての幼児や小学校1年生が、豊かな心情、学ぼうとする意欲、健全な生活態度といった「学びの土台」を身に付けられるよう取り組んでまいります。
さらに、児童期から本を読むことの楽しさを知り、生涯にわたって本に親しめる読書習慣を身に付けるため、「電子図書整備事業」として、全児童に配付したタブレット端末を活用し、児童が自主的に、いつでも、どこでも、好きなだけ、気軽に本を読むことができる環境を継続してまいります。
人口減少下にある本市にとって、将来世代の育成は大変重要となっております。令和6年度に配置した「学力向上推進監」による各校の実態に応じた具体的な指導や助言を継続するとともに、指導力のある教員による授業公開を活用した研修・検討の場を設けるほか、全国平均との差が大きい算数・数学に関する研修を強化し、教員の指導力向上を図ってまいります。
また、年2回実施する標準学力調査の結果を踏まえた授業改善を推進することで、令和6年度、小学校において、平成19年の調査開始以来初めて、仙台市を除く県平均を上回った全国学習状況調査の正答率を、更に全国平均に近づけることを目標に、子どもたちが主体的に学べる環境づくりに引き続き取り組んでまいります。
さらに、子どもたちがこれからの社会を主体的に生き抜くためには、知識や技能だけでなく、思考力、判断力、表現力を活かし、社会性や責任感を養っていくことが必要です。「学校わくわくプラン推進事業」として、児童生徒の学習や活動意欲を高める取組や学校と家庭、地域が連携・協働した活動と基礎学力の充実とが相まって、児童生徒一人ひとりが自己の可能性を発揮し、他者との共生を通じて自己肯定感を高められるよう取り組んでまいります。
「石巻市子どもの体力向上プラン」に基づき、「体力向上推進事業」として、各学校の実態に応じたアクションプランを作成し、体力・運動能力向上に取り組むとともに、石巻専修大学と連携し、身体組成と運動能力の関連性を科学的根拠に基づいて分析を行い、AIによる運動解析アプリを各学校に導入し、体育の授業で活用するなど、運動に親しみながら目標に向かって継続的に努力する児童生徒の育成に取り組んでまいります。
また、全ての児童生徒が安心して学校生活を送ることができるようにするため、小中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒に特別支援教育支援員を配置し、学習活動や学校生活で、困り感を抱えた児童生徒に寄り添いながら支援を行い、学級担任等が円滑に授業を進められるよう支援してまいります。
併せて、校務支援システムの導入により、教員が児童生徒と向き合う時間をより多く確保するとともに、授業準備に専念する余裕が生まれる環境を整えることで教育の質を高め、教員の指導力向上を図ってまいります。
食材料費の高騰に対応するため、「保育施設利用者給食費負担軽減事業」及び「学校給食保護者負担軽減事業」に継続して取り組み、利用者や保護者の負担を増やすことなく、質と量が保たれた給食を提供するとともに、安全で安心な学校給食を安定的に供給するため、老朽化が進む住吉・河北・河南の各学校給食センターを統廃合し、PFI方式による「新学校給食センター」の令和9年4月の供用開始を目指し、整備を進めてまいります。
また、少子化に伴い、適正規模を下回る学校が市内全域で増加してきていることを踏まえ、地域の実情に配慮しつつ、PTAや保護者をはじめ、地域住民も含めて意見交換を重ね、小中学校の適正規模と適正配置の実現に向けて引き続き取り組んでまいります。
さらに、蛇田中学校の屋上防水や給水設備の改修のほか、開北小学校の構造体及び地質調査の実施、前谷地小学校屋内運動場の改築工事に取り組んでまいります。
次に、「移住促進と関係人口の創出」に向けた取組といたしましては、移住を希望する方々に、本市の豊かな自然や文化などをはじめ、暮らしやすさを知ってもらうため、「移住定住推進事業」として、特に首都圏や県内の大学に通う学生に対しその魅力を発信し、移住の検討から移住後の様々な不安などを気軽に相談できる窓口を設置するとともに、生活の具体的なイメージをつかんでいただけるお試し移住体験事業などをはじめとする包括的な支援により、移住・定住を促進してまいります。
また、本市の魅力を市内外に伝えるとともに、東日本大震災で御支援いただいた全国の皆様へ感謝の気持ちを伝えるため、「ロゴマーク活用事業」として、市内事業者によるロゴマークを活用したシティプロモーション活動を支援し、民間事業者と連携して、本市の認知度向上とシビックプライドの醸成を目指すとともに、本市を象徴する新たなシンボルとして広く浸透させてまいります。
次に、「持続可能な公共交通ネットワークの整備」に向けた取組といたしましては、日常の移動手段として選ばれる公共交通を目指すため、住民バスの路線再編を進めるとともに、運転免許証返納者に対する路線バスの運賃割引制度を創設し、運転免許証返納者の移動費用負担の軽減及び路線バスの利用促進に取り組んでまいります。
また、石巻駅前広場及びかわまち交流拠点に設置するデジタルサイネージを活用し、鉄道、バス等の運行時刻表や経路図を掲載するほか、観光情報やイベント情報等を発信し、公共交通をより利用しやすくする環境を整備してまいります。
次に、「地域コミュニティの充実と強化」に向けた取組といたしましては、多様化する地域課題の解決や住民主体の活力ある地域づくりを図るため、「ずっと住みたい地域づくり支援事業」として、市内16地区全てに住民自治組織の設立を目指して取り組んでまいりました。これまで12地区で設立されており、残る4地区の早期設立に向けた支援を継続するとともに、住民の意識醸成を図りながら、「自助・共助・公助」を基本に、地域の特色や住民の力を活かした住民自治組織の活発な活動を促進してまいります。
4.産業の発展と雇用創出
四つ目は、「産業の発展と雇用創出」についてであります。
本市は、豊かで魅力あふれる地域資源を有し、漁港や港湾などの産業基盤も整っており、第一次産業から第三次産業までがバランスよく発展してまいりました。しかしながら、少子高齢化の加速、気候変動による自然災害の頻発、さらには物価高騰の影響など、複合的な課題に直面しています。特に、水産業においては、漁獲量の減少や燃料費の高騰に加え、ALPS処理水の海洋放出に伴う風評被害が深刻な影響を与えています。
こうした状況を打開し、稼ぐ力を強化していくため、地域資源の活用、販路の拡大、担い手の確保・育成をはじめ、企業の経営体質強化や新たな価値の創造に取り組む事業者の支援、雇用の場を確保するための企業立地の促進や創業支援に取り組んでいく必要があることから、次の各施策に取り組んでまいります。
まず、「地場産業の支援・高度化」に向けた取組といたしましては、本市の優れた農林水産物のブランド力の向上等を図るため、石巻市6次産業化・地産地消推進センターによる販路拡大や地域資源の高付加価値化による新商品開発及び新ブランド確立の支援に取り組むとともに、輸出スキルの向上、地域が輸出しやすい環境づくりを推進し、アメリカ向け輸出を主軸とした体制強化を図るため、石巻食品輸出振興協議会の活動を引き続き支援してまいります。
また、石巻地域産学官グループ交流会などの機会を活用し、今後、新たな利用が期待される新素材や新技術の活用について、関連事業者と連携しながら普及啓発と事業化に向けた取組を推進してまいります。
さらに、東北大学との連携によるイノベーションの創出を目指し、「次世代放射光施設 ナノテラス」を活用できる環境を整備するとともに、施設利用を通じた製品性能の向上や差別化を図るなど、先端技術の活用による新たな市場開拓や付加価値の創出を支援し、地元企業の発展につなげてまいります。
また、ナノテラスを利用して得られた成果をもとに研究開発等に取り組む事業者を支援してまいります。
併せて、企業の経営体質の強化や新たな事業展開等を図るための「プロフェッショナル人材雇用助成金」により、引き続き企業の成長戦略を具現化していく人材の雇用を促進してまいります。
水産分野におきましては、災害復旧事業等完了後の漁港利用状況の変化や自然状況の変化に対応した機能強化、改良及び整備を引き続き進め、漁業従事者の就労環境の改善や安全性の向上に取り組んでまいります。
また、水産業界にとって大きな試練となっているALPS処理水の海洋放出、海洋環境の変化等の諸問題に対応するため、長期的視点に立った支援等の要望に加え、水産業における流通・生産の拠点としての機能強化等、特定第三種漁港市長協議会等の構成自治体との連携を強化してまいります。
さらに、石巻漁港の環境整備はもちろんのこと、石巻魚市場の水揚げ高の増加や水産加工業者への安定した原料供給等を図るため、県や各種協議会等に対し、環境改善や安全性の向上について要望するとともに、県内外の船主・生産者組合等への漁船誘致活動を継続的かつ効果的に実施してまいります。
石巻くじら振興協議会の活動を通じ、本市の伝統的な食材である鯨肉の消費拡大等を図るとともに、本市での開催が4年ぶりとなる「全国鯨フォーラム2025石巻」において、本市の鯨食文化を全国に発信し、その普及や継承の推進をアピールしてまいります。
また、地球温暖化の影響等による海水温の上昇を踏まえ、海洋環境の影響を受けにくい陸上養殖の普及を促進するため、「陸上養殖システム導入支援事業」として、参入事業者に対し、導入経費の一部を助成してまいります。
農林業分野におきましては、高齢化や担い手不足、気候変動による影響をはじめとする多くの課題を抱えている状況を踏まえ、環境に配慮しつつ、生産性向上を図る取組が求められています。
食や環境への関心の高まりを受け、世界の有機食品の売上は増加を続け、国内市場の拡大傾向を踏まえると、オーガニック農法は、農業が持続的に発展していくための有効手段の一つとなりますことから、有機農業の普及、啓発に向け、「有機農業産地づくり推進事業」として、「有機農業実施計画」を策定し、石巻市オーガニックビレッジ宣言を見据えた取組を進めてまいります。
また、石巻市産の木材需要の拡大により、本市の木材加工企業や林業者等、木材産業界の振興を図るため、「石巻市産木材利用住宅促進事業」として、石巻市産の木材を一定量以上使用して一般住宅を新築する施主に対し、建築費用の一部を助成してまいります。
次に、「第一次産業における担い手の育成」に向けた取組といたしましては、若者や就業希望者に対し、本市の第一次産業の魅力を発信するとともに、「担い手育成総合支援事業」により、就業相談から就業・独立支援、さらには就業後のフォローアップ活動等を実施し、就業者の受入体制を整えるとともに、その定着を促進するための支援に引き続き取り組んでまいります。
次に、「企業立地と新規創業の促進」に向けた取組といたしましては、本市に新しい企業を呼び込むため、企業の多様なニーズに応えられる環境づくりを行うとともに、県内外の企業に対し各種優遇制度や本市独自の助成制度をPRするなど、引き続き私が先頭に立って、積極的な企業誘致活動を推進してまいります。
また、本市産業の多様性・競争性の創出と雇用の場の確保を図るため、「産業振興対策事業」として、関係機関との連携を図りながら、創業気運の醸成をはじめ、創業準備期から創業後に至るまでの包括的な支援を継続していくほか、「創業者フォローアップ事業」として、創業後における経営安定化の支援に取り組んでまいります。
次に、「全世代の就労対策と支援」に向けた取組といたしましては、若者の地元定着を促進するため、高校生を対象とした合同企業説明会や地元企業見学会など、将来のキャリアを考えるきっかけとなる機会を提供し、地元就職につなげてまいります。
さらに、高齢者の豊富な経験と知識を社会に活かすため、引き続き、高齢者向けの合同企業説明会を開催し、働く意欲のある高齢者と働く場の掘り起こしに取り組むなど、関係機関等と連携を図りながら、年齢にかかわらず能力を発揮できる環境を整備してまいります。
5.物流拠点の形成と新たな観光の構築
五つ目は、「物流拠点の形成と新たな観光の構築」についてであります。
本市の産業・経済の活性化、観光・文化の振興、さらには高度救急医療体制や災害時における緊急輸送・物流機能の強化といった面において、道路網や港湾の果たす役割は大きく、非常に重要なものとなっております。
また、豊かな自然や多彩な食材と歴史・文化が織りなす、魅力ある地域資源を様々な形で発信し、新たな観光ルートの構築による観光振興を進めていくため、次の各施策に取り組んでまいります。
まず、「物流機能の強化」に向けた取組といたしましては、これまでの粘り強い要望活動によって、国際拠点港湾「仙台塩釜港石巻港区」における耐震強化岸壁の整備が進められているところですが、石巻港においては、三陸沿岸道路や石巻新庄道路などの陸路と海路の結節点となる、石巻港を核とした物流拠点都市の形成のほか、防災拠点としての更なる機能強化に向け、官民挙げた要望活動を展開するとともに、石巻港の利用促進を図るため、港湾管理者等と連携したPR活動を展開してまいります。
また、宮城県が策定した「仙台塩釜港港湾脱炭素化推進計画」においても、石巻港区は東北地方の物流拠点として重要な役割を担っていることから、港湾の競争力強化と脱炭素社会に向けた取組による地域経済の活性化のため、国・県との連携を一層強化してまいります。
さらに、産業・経済の活性化はもとより、地域間連携による観光ネットワーク形成や物流の効率化が大いに期待できる、石巻新庄道路の早期実現に向け、関係自治体と国・県への働きかけを進めていくとともに、国道108号石巻河南道路の整備を促進してまいります。
次に、「新たな観光資源の構築と情報発信の強化」に向けた取組といたしましては、首都圏や仙台圏でのイベントブース出展やSNSによる情報発信など、従来の方法にとらわれず、活用可能な媒体を幅広く利用するとともに、市内外で開催される各種イベント等で「いしのまき観光大使」に協力を依頼するなど、多様な手法により本市をPRし、観光誘客に取り組んでまいります。
また、せんだい・宮城フィルムコミッションと連携し、本市を舞台とした映画やドラマ、CM等のロケーション撮影を誘致するとともに、映画等のプロモーションやロケ地マップの作成にも積極的に関わることで、本市の魅力をより効果的に発信してまいります。
さらに、首都圏をはじめ県外等で開催される物産展等のイベントに出店する事業者に対し、「石巻市物産展等参加支援補助金事業」として、参加経費の一部を支援することで、本市特産品等のPRと販売促進を図り、地域経済の活性化を推進してまいります。
仙台塩釜港石巻港区への大型客船誘致活動を積極的に行い、国内外からの観光誘客を推進するとともに、寄港時には市民一体となった歓迎イベントを開催するなど、国際拠点港湾を活かした地域活性化に取り組むほか、日本遺産「みちのくGOLD浪漫」に「金華山道」及び「金華山詣」が認定されたことを契機として、金華山への来島者数の増加に伴い、定期船の増便が求められていることを踏まえ、増便に要する経費の一部を助成することにより、金華山へのアクセスを充実させてまいります。
また、巳年と縁が深い「金華山黄金山神社」において、巳の年、巳の月、巳の日、巳の刻(本年5月12日午前)を期して斎行される本祭を間に、本年3月から10月まで「巳歳御縁年大祭」が斎行されます。現在、本市博物館では、金華山にスポットを当てた企画展「みちのくの金と金華山」を開催しており、多くの方々に金華山を訪れていただく機会につなげていけるよう、大祭の機運を盛り上げるとともに「みちのくGOLD浪漫」の更なる魅力の発信に努め、観光地として一層のイメージアップを図ってまいります。
中心市街地の回遊性の向上による賑わいの創出を図るため、「中心市街地賑わい創出事業」として、中心市街地への新規出店をワンストップで支援する「街なか出店サポートセンター」を設置するとともに、空き地・空き店舗を活用した事業や街なかで開催するイベント等の支援により、中心市街地にしかない魅力を引き出すことで、市民や観光客の目的地となる店舗や居場所を増やし、誰にとっても居心地がよい、歩きたくなる楽しいまちを目指してまいります。
また、令和6年度に引き続き、中心市街地に観光客の撮影スポットになるようなマンガモニュメントと一体化したベンチを設置し、マンガの街としての魅力を更に高め、石巻駅前広場及びかわまち交流拠点に設置するデジタルサイネージにより観光情報や中心市街地の情報等を発信するとともに、水辺のすばらしさを感じ、安全で快適に散策できる「いしのまき水辺の緑のプロムナード」を観光資源として、各種イベント開催等に積極的に活用してまいります。
さらに、「文化財ガイドボード等整備事業」として、旧観慶丸商店をはじめとした案内板設置のほか、本市の歴史や東日本大震災の被害状況等を後世に末永く伝えていく説明板を設置することで、本市の歴史と文化に触れることができる、中心市街地ならではの魅力を創出し、市民や観光客が行き交う活気を生み出してまいります。
6.広域連携体制の強化
六つ目は、「広域連携体制の強化」についてであります。
全国的に人口減少、少子高齢化が進んでいる中、各市町が有する機能、資源を有効活用し、住民が安心して暮らし続けることができるよう、様々な分野において連携・協力しながら圏域全体の活性化を図り、住民はもとより移住者の定住を促進することで、石巻圏域が将来にわたって持続していくため、諸施策に取り組んでまいります。
まず、「圏域における移住定住の促進」に向けた取組といたしましては、首都圏で開催される移住相談イベントにおいて、圏域のスケールメリットを活かした魅力発信に取り組むほか、若者や子育て世代をターゲットとした移住体験ツアーを実施するなど、引き続き連携して取り組んでまいります。
次に、「圏域における交流人口の拡大」に向けた取組といたしましては、一般社団法人石巻圏観光推進機構との連携、協力体制を一層強化し、通過型から滞在型観光への転換に向け、みちのく潮風トレイルや教育旅行の事業周知を積極的に行いながら、引き続き受入れ環境の整備、地域資源を活用した広域観光を推進してまいります。
次に、「持続可能な地域社会の構築」に向けた取組といたしましては、SDGsシンポジウムの開催をはじめ、ビーチクリーン活動や圏域SDGsパートナー企業を対象としたセミナーの実施など、SDGsの理念を広く普及させる取組を進め、圏域住民一人ひとりが主役となり、これまで以上に連携・協力を深めながら、SDGsの視点に基づいて地域課題を解決し、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。
また、震災伝承みやぎコンソーシアムへの参加やいしのまき防災・伝承コミュニティとの連携を図りながら、震災伝承施設等を相互にPRし、震災伝承の推進に取り組んでまいります。
行財政運営
次に、「行財政運営」についてであります。
限られた行財政資源を活かした持続可能な行財政運営を推進していく必要がありますので、各種施策に取り組んでまいります。
まず、「市民サービスの向上」に向けた取組といたしましては、市民からの意見や提案等を市政に反映させるため、引き続き、市長への手紙、市民意識調査、動く市長室、まちづくり懇談会等を実施し、市民の皆様と共に未来を見据えたまちづくりを進めてまいります。
また、次世代を担う若者に石巻の将来を考えていただくなかで、郷土に対する愛着と誇りを持っていただくため、いしのまき政策コンテストを開催するほか、子どもたちが意見表明を行う場を確保するため、まちづくりについてアイデアを出し合い、社会に発信する取組を引き続き実施してまいります。
さらに、光ファイバーの提供が困難な、田代島・網地島において、情報格差の解消を図り、生活環境の向上を図るため、「離島通信環境整備助成事業」として、人工衛星など新たな技術を活用した高速インターネット環境を整備する市民に対し、設置に要する経費を助成してまいります。
併せて、従来から取り組んでいる行政手続における電子申請の更なる拡充に取り組むとともに、通知文書のデジタル化の検討を進め、DXを一層推進することで業務の効率化を図り、より迅速で便利な行政サービスを提供し、市民の皆様にとって身近で利用しやすい市役所の実現を目指してまいります。
次に、「持続可能な行財政運営の推進」に向けた取組といたしましては、事務事業評価が令和4年度の試行実施から3年目を迎え、これまでの評価結果や取組実績の比較検証を踏まえた更なる改善に努め、「第2次総合計画基本計画」の各種指標の評価・検証を引き続き実施し、PDCAサイクルの確立を着実に進めていくとともに、現在策定を進めている令和8年度を起点とする後期基本計画において、市民満足度調査で得られた結果などを踏まえた重点改善分野への取組を強化する施策の立案を検討してまいります。
また、その施策がどのように実行され、どのような成果を上げているのか、その可視化に努めてまいります。その内容を市民の皆様に丁寧に説明し、信頼をいただくことが重要となりますことから、ロジックモデルにより、達成したい最終的な目標を明確にするとともに、その成果へつながる活動を的確に評価できるシステムを構築し、予算執行に基づく成果と併せた検証により、市民ニーズを捉えた施策のブラッシュアップを的確に行い、第2次石巻市総合計画に掲げる本市の将来像である「ひとりひとりが多彩に煌めき共に歩むまち」の実現を目指してまいります。
さらに、本市が直面する厳しい財政状況や社会環境の変化に対応するためには、本市が持つ経営資源をこれまで以上に集中的かつ効率的に活用していくことが必要不可欠であります。令和7年度を終期とする「石巻市行財政改革推進プラン2025(ニーゼロニーゴ)」に掲げた目標の達成に向けて、引き続き全庁を挙げて取り組むとともに、その検証・分析結果について、令和8年度以降を見据えた次期プラン「2030(ニーゼロサンゼロ)」に反映し、長期的な視点での行政目標を明確にし、社会情勢や市民ニーズの変化を的確に捉え、持続可能な財政基盤の構築と質の高い公共サービスの提供を目指してまいります。
社会保障経費の増大、復興事業で新たに整備した公共施設の維持管理経費の増加や老朽化対策など、今後更に財政需要が高まる状況を踏まえ、歳入の確保策として、「債権管理基本方針」に基づく債権の適正管理、遊休資産の売却、国債等の債券による基金の運用に取り組むとともに、ふるさと納税制度を活用した、がんばる石巻応援寄附金についても、より魅力的な返礼品の提供、掘り起こしを行い、寄附金額の更なる増加に取り組んでまいります。
いずれにいたしましても、各種政策・施策や事業につきましては、EBPM(証拠に基づく立案)による予算の中身の重点化や優先順位づけを行い、効果的・効率的な支出を徹底することで、予算・政策等の質の向上を図ってまいります。
予算編成
次に、予算編成について申し上げます。
令和7年度当初予算編成に当たりましては、健全で持続可能な財政基盤の確立を基本方針とし、歳入に見合った歳出予算、コスト意識の徹底及び厳選した事業の推進の3つの方針を掲げ、限られた財源の中、健全で持続可能な財政基盤の確立と施策の推進の両立を目指した予算編成を行うことといたしました。
この結果、令和7年度予算は、「一般会計」で、767億円、「水産物地方卸売市場事業特別会計」をはじめとする4特別会計で、346億円、「病院事業会計」で、63億円、「下水道事業会計」で、142億円、全会計の総額で、1,318億円となっております。
組織機構の見直しにつきましては、東日本大震災の最大の被災地として、自助・共助・公助の取組による「災害に強いまちづくり」の更なる推進が求められます。
現組織を基本としながらも、昨今の異常気象による自然災害の激甚化や巨大地震への備え、地域防災の担い手の育成、女川原子力発電所の再稼働に伴う避難計画の実効性の更なる向上に対応するため、「危機管理」に特化した部を新設し、防災力を更に高めるとともに、防犯・交通安全対策を一体化させた取組を進め、市民一人ひとりの力を結集し、共に学び、備えることで、地域全体の安全安心を強化してまいります。
以上が令和7年度に臨む私の基本姿勢と令和7年度予算案であります。
むすび
市長就任から今日まで、新型コロナウイルスによるパンデミックとロシアによるウクライナへの軍事侵攻という、世界的な危機が重なり、様々な制約下における市政運営は大きな試練となりましたが、座右の銘である「忘己利他」、「己を忘れ他を利するは慈悲の極みなり」の思いを更に強くし、身を粉にして奔走してまいりました。
しかしながら、本市の最重要課題として、これまで様々な対策を講じてきた「人口減少対策」は、基礎自治体としての限界もあり、いまだ十分な成果が得られていない状況であります。
人口減少は日本全体が直面している構造的課題であり、労働力不足による経済活動の停滞をはじめ、その影響は地域社会のあらゆる面に波及し、これまでの社会システムをも揺るがしかねない重大な問題となりつつあります。
この状況を踏まえ、本市が抱える諸課題に向き合いつつ、国が次の10年を見据えて起動する「地方創生2.0」にかかる施策を強力に推進し、人口減少のスピードをいかに抑制し、安定化させていくことが、本市の歴史や伝統・文化を継承し、未来へつなげるための重要な鍵ともなります。
また、100年・200年に一度と言われる経済・社会基盤の転換によって、私たちの日常生活は大きく変わろうとしています。
DXの推進による行政サービスのオンライン手続やリモートワークなどをはじめとする新たな環境を、幅広い分野に積極的に取り入れていくことで、書かない、行かない窓口の構築による市民サービスの更なる向上を図るとともに、柔軟な働き方を可能とする環境が整い、結婚や子どもを持ちたいとの希望をかなえることや地元への就職などの好循環につなげるなど、地域の実情に即した取組をしっかり進めていくことで、成長へのチャンスに変えて行くべきではないでしょうか。
こうした思いで様々な取組を重ねれば重ねるほど、私の目指す理想の実現に向けて、更なる熱い気力と責任感が湧いてまいります。
令和7年度は、これまで述べてまいりました6つの重点施策に、引き続き揺るぎない決意をもって取り組み、「人口減少の抑制」、「稼ぐ力の強化・創出」、「将来世代の育成」を強力に推進してまいります。
併せて、自然災害の頻発、激甚化を踏まえ、災害に強いまちづくりに着実に取り組み、市民の皆様が安全で安心して暮らすことができるまちづくりを目指してまいります。
人口減少をはじめ山積する諸課題にオール市民で対応し、「全ての市民が住むことに誇りを持てるまちづくり」に全身全霊で取り組み、市民の皆様の幸せと「飛躍と誇れる石巻」を期して、私の愛する「ふるさと石巻」の輝かしい未来に希望をつないでまいります。
結びに、市民の皆様のお力添えと議員各位のより一層の御理解、御協力を賜りますよう衷心よりお願い申し上げまして、令和7年度の施政方針といたします。
このページへの問い合わせ
部署名:復興企画部 政策企画課
電話番号:0225-95-1111
企画調整担当
政策推進担当