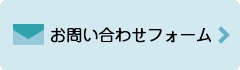東部地区復興まちづくりについて
更新日:2014年10月3日
1. 背景と目的
現在、東日本大震災による被災から1日も早い復興に向けて、土地区画整理事業や防災集団移転促進事業等の実施により、本市の復興まちづくりは進められています。
しかしながら、本市にはこれらの事業が行われない地区においても、津波被害の大きい市街地が存在しており、これらの地区において、復興まちづくりの遅れとそれに伴う住民の流出、地域の活力低下、コミュニティの崩壊等が問題となっています。
このような地区において、どうすれば住民の皆さんが安全に安心して暮らし続けられることができるのか、また、地区外にいらっしゃる方々がどうすれば戻ってくることができるのかについて、住民の皆さんといっしょに考えながら、復興まちづくりを進めていくこととしました。
2.基本的な考え方と目標
- 東部地区の復興まちづくりは、津波被害等からの「安全・安心」、地域力の主体である「健全なコミュニティ」、防災面以外の様々な住環境をよくする「住みやすさ」が基本となると考えています。
- 意見交換会やアンケート調査を通して、復興まちづくりに対する住民の皆さんのご意見を聴き、様々なご意見をとりまとめ、次のステップにつなげる形にします。
3.ブロック別意見交換会等の開催
- 平成25年11月28日より、湊地区・渡波地区において意見交換会を実施し、平成26年2月28日までに、第1回は7地区、第2回は8地区においてのべ15回開催しました。(日程については関連ファイル「意見交換会開催日程」のとおり)
- 第1回意見交換会を開催した平成25年12月以降、被災時に湊地区・渡波地区に居住していた方を対象に、アンケート調査を実施しました。(結果については、3-1「アンケート結果の概要」及び関連ファイル「アンケート結果(全体)」を参照ください。)また、第1回意見交換会開催時にご要望が多数ありました、今後想定される「津波予測(シミュレーション)」について、説明会を開催しました。(3-2「津波シミュレーションの説明会」を参照ください。)
3-1 アンケート結果の概要(詳細は、アンケート結果(全体)参照)
| 区分 | 回答数(回答率) | 2,661通(46.1%・配達総数は5,771通) |
| 問1 | 現在のお住まいについて | 被災前から継続して住んでいる方は約6割であり、応急仮設住宅やみなし仮設に住んでいる方は3割弱となっています。 |
| 問4 | 地区を離れたい理由について | 7割以上の方が、「また津波が来ることに対して不安がある」をあげています。次いで、「生活に必要な施設等が少なくなった」が3割弱です。 |
| 問7 | 住み続けるために重要と考える施設 | 「安全な避難場所や充分な備蓄」が最も多く、半数を超えています。次いで「津波からまちを守る堤防」「病院やクリニックなどの医療施設」の順になっています。 |
| 問9 | コミュニティの再生や維持のために重要と思うこと | 「町内会や自治会などの組織の強化・充実」が最も多く、次いで「若い世帯など、新しい住民が増える」「地域から離れて住んでいる人が早く戻ってくる」の順になっています。 |
| 問10 | 安全・安心のために有効と思う活動 | 6割の方が、「自主防災組織等による見回りや声かけ」をあげており、次いで「避難するときに支援が必要な人の把握」と続いています。 |
3-2 津波シミュレーションの説明会
- 第1回意見交換会にてご要望の多かった、津波シミュレーションについての説明会を、以下の日程で行いました。(説明会資料については、関連ファイル「津波シミュレーション説明会資料」を参照ください。)
| 日時 | 平成26年1月29日(水曜日)午後7時より午後8時30分まで |
| 会場 | 石巻市立万石浦中学校体育館(石巻市流留字七勺21) |
| 内容 | 津波シミュレーションについて(東北大学災害科学国際研究所 今井先生からの説明)、質疑応答 |
4.意見交換会の結果について
- 平成25年11月より湊地区・渡波地区で開催された意見交換会にて、出席された方々からいただいたご意見等を取りまとめたリーフレットを各地区ごとに作成し、該当する地区にお住いの方々へ回覧を行いました。今後は、いただいたご意見を参考にさせていただき、震災復興基本計画実施計画に反映させるなど、具体化させていきたいと考えております。
- 各地区のリーフレットについては、下記リンクより参照ください。
- 渡波南 渡波中 渡波北 栄田・黄金浜
- 根岸 松並・緑 伊原津・鹿妻 吉野・御所入・湊町
- 榎壇 不動町
関連ファイル
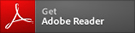 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 地域協働課
電話番号:0225-95-1111
行政委員担当
町内会担当
住居表示・地縁団体担当
ずっと住みたい地域づくり支援事業担当
地域づくり基金担当
コミュニティセンター(利用受付)担当
その他の問い合わせ先
基盤整備課施設計画第1グループ
内線(5517、5516)