読み飛ばし用リンク
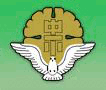 石巻市立中津山第一小学校
石巻市立中津山第一小学校- 表示色
- 標準
- 黒(ハイコントラスト)
- 灰(ローコントラスト)
トップページ > すごいぞ!中一小学区 > 歴史 > 神取駅跡
神取駅跡
更新日:2020年12月11日
神取駅跡
慶長・元和年間の北上川改修後、伊達藩では奥州街道の他に脇街道として気仙道(明治から東浜街道)を開設しました。仙台から七北田ー利府ー高城ー小野ー鹿妻ー和渕ー寺崎ー柳津ー横山ー志津川ー大谷ー気仙沼を経て気仙郡唐丹に至る街道で、領内における浜街道・縦貫道としての性格を有しています。主要地におよそ3里(約12km)ごとに宿駅が設けられ、桃生町内では神取と寺崎に置かれました。
宿駅は郡奉行の支配下にあって、肝入・検断・馬差(馬指)などの役人が宿駅内を取り締まり、継立などのために駕籠や人馬を常備し、次の駅から次の駅へと馬を取り換え、人を交代させました。これを利用できるのは、公用の役人や侍達だけで、一般の人は簡単には使えませんでした。
神取に宿駅が置かれたのは、幕末の天保以降でした。
慶長・元和年間の北上川改修後、伊達藩では奥州街道の他に脇街道として気仙道(明治から東浜街道)を開設しました。仙台から七北田ー利府ー高城ー小野ー鹿妻ー和渕ー寺崎ー柳津ー横山ー志津川ー大谷ー気仙沼を経て気仙郡唐丹に至る街道で、領内における浜街道・縦貫道としての性格を有しています。主要地におよそ3里(約12km)ごとに宿駅が設けられ、桃生町内では神取と寺崎に置かれました。
宿駅は郡奉行の支配下にあって、肝入・検断・馬差(馬指)などの役人が宿駅内を取り締まり、継立などのために駕籠や人馬を常備し、次の駅から次の駅へと馬を取り換え、人を交代させました。これを利用できるのは、公用の役人や侍達だけで、一般の人は簡単には使えませんでした。
神取に宿駅が置かれたのは、幕末の天保以降でした。

「神取駅跡」の標柱

駅跡から気仙道(東浜街道)を臨む
