読み飛ばし用リンク
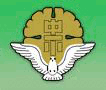 石巻市立中津山第一小学校
石巻市立中津山第一小学校- 表示色
- 標準
- 黒(ハイコントラスト)
- 灰(ローコントラスト)
トップページ > すごいぞ!中一小学区 > 地域の由来 > 神取
神取
更新日:2021年1月7日
神取
起源には、2つの説があります。
1 水乎揖取(かこかんどり)説
元和年間の北上川開削工事で、北上川・迫川・江合川を合わせた三河川の水量が、狭い流路を通るため下が深い淵となり、大きな輪になって渦巻いていました。この難所を乗り切るためには、熟練した舵取りが必要で、舵を取る人=揖取(かんどり)が多くいた、という説です。
ちなみに「下が深い淵となり、輪になって渦巻いていた」所を「輪淵」と言ったのが「和渕」の起源だそうです。
2 香取説
昔、関東地方から移住してきた人が、故郷の香取神社を祭ったから、と言われています。今の和渕地区に「香取伊豆御子神社」が建てられ、そこを香取と呼んでいました。いまの八反崎地区と考えられます。その後天保3年(1832年)の北上川の工事で、今の神取地区に移住してきました。
江戸時代後期には、気仙道(東浜街道)の宿場町となり、神取駅として栄えました。
起源には、2つの説があります。
1 水乎揖取(かこかんどり)説
元和年間の北上川開削工事で、北上川・迫川・江合川を合わせた三河川の水量が、狭い流路を通るため下が深い淵となり、大きな輪になって渦巻いていました。この難所を乗り切るためには、熟練した舵取りが必要で、舵を取る人=揖取(かんどり)が多くいた、という説です。
ちなみに「下が深い淵となり、輪になって渦巻いていた」所を「輪淵」と言ったのが「和渕」の起源だそうです。
2 香取説
昔、関東地方から移住してきた人が、故郷の香取神社を祭ったから、と言われています。今の和渕地区に「香取伊豆御子神社」が建てられ、そこを香取と呼んでいました。いまの八反崎地区と考えられます。その後天保3年(1832年)の北上川の工事で、今の神取地区に移住してきました。
江戸時代後期には、気仙道(東浜街道)の宿場町となり、神取駅として栄えました。

住民バス・神取バス停

神取山城跡

西八反崎から見た神取山

神取駅跡

香取伊豆御子神社(和渕神社)

「香取伊豆御子神社」の表示
