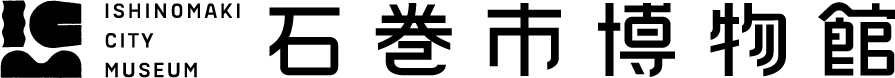大小暦
更新日:2025年8月5日
毎年の月の大小は、江戸時代の好事家の遊び心を満足させる格好の材料でした。そこから、さまざまな着想による大小暦が生まれました。大小暦は、その年の大小の配列を言葉や絵で表現し、1枚の摺り物にしたものです。商品として売られた物ではなく、各人が趣向に合わせて作り、年始の引き出物として友人・ 知人に配ったものです。
写真の大小暦は、屏風に大の月(ここでは2月・3月・4月・7月・9月・11月) 小の月(閏2月・5月・6月・8月・10月・12月)の文字が書かれており、床の間の前の鏡餅にネズミが乗っているので、子年を表しています。
これらのことから、この暦は嘉永5年(1852年)のものとわかります。

大小暦