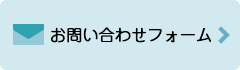国民健康保険限度額適用認定証
国民健康保険に加入されている方(75歳未満)で入院や外来診療を受ける場合、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の自己負担額を一定の金額に抑えることができます。マイナ保険証をお持ちではない方で入院や高額な外来診療を受ける場合には、事前に交付申請をしてください。
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から移行することを選択できます。)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになりますので、「後期高齢者医療制度(外部リンク 宮城県後期高齢者医療連合会)」をご覧ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額認定証の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。なお、マイナンバーカードで受診できる医療機関において、資格確認書等を提示して情報提供に同意した場合も同様の取扱いとなります。「マイナンバーカードの保険証利用について」もご覧ください。ただし、次の方は事前に申請が必要となります。1、システムが導入されていない医療機関での受診の方
2、石巻市に転入して国保に加入した方、職場の健康保険の脱退などにより国保に加入した方で、すぐに高額な外来や入院をする予定のある方
医療機関では加入手続きをしてすぐには自己負担限度額を確認できません。また、4月から7月までは前々年、8月から翌年3月までは前年の世帯主と国保加入者全員の所得で判定するため、当時他市で課税されていた方が世帯にいる場合、区分の確認ができない可能性がありますのでお問い合わせください。
3、非課税世帯で申請月前12か月以内に90日を超える入院をしていて、食事療養額の減額の対象となる方
非課税世帯(70歳未満 区分「オ」、70歳以上 区分「低2」の世帯)で、入院日数が90日を超えたときには申請することによって入院時食事代の標準負担額が変更になります。
詳しくは「入院時の食事代について」をご覧ください。
自己負担限度額は、所得区分と年齢により異なります
詳しい区分については下記をご覧ください。・70歳未満の方の自己負担限度額
・70歳以上の方の自己負担限度額
該当区分についてはお問い合わせいただくか、保険年金課または各支所・各総合支所市民福祉課へ相談にお越しください。
原則、保険税の滞納が無い世帯に発行するものとなります。納期限が到来している国民健康保険税の未納がある世帯については、国民健康保険法の規定により、限度額適用認定証の交付ができない場合がありますのでご注意願います。
参考
マイナンバーカードが保険証として使えます(外部リンク デジタル庁)
マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク 厚生労働省)
申請に必要なもの
- 国保資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)の確認ができる物(世帯主、治療を受ける方)
- 本人確認書類(手続きに来る方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
- 国民健康保険限度額適用認定申請書
- 別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要となります。(PDF:63KB)
- 住民税非課税世帯 70歳未満 区分「オ」、70歳以上 区分「低2」の世帯で、過去12か月以内に入院日数が90日を超えるときは入院日数のわかる領収書
その他
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の方は、別途「特定疾病療養受療証」の交付手続きが必要です。詳しくは特定疾病療養のページをご覧ください。
既に支払い済みの医療費については、高額療養費のページをご覧ください。
医療費の自己負担限度額区分
外来診療の限度額適用は、月ごと・医療機関ごとに別々の取扱いになります。また、同じ月内でも、外来と入院は別々の取扱いになります。
|
所得要件 |
区分 |
限度額 |
4回目以降 |
|
所得(注1)901万円超え |
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
所得600万円超え901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
所得210万円超え600万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
所得210万円以下(住民税非課税は除く) |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯(注2) |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
(注1) 「所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
(注2) 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方
- 4回目以降の限度額とは、過去12か月間で同一世帯で限度額まで達した回数が4回以上あった場合です(多数回該当)。
| 所得要件 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 交付申請 | ||
| 現役並み 所得者 | 課税所得(注1)690万円以上 | 現役並み3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 4回目以降 140,100円 |
× |
|
| 課税所得380万円以上 | 現役並み2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 4回目以降 93,000円 |
〇 |
||
| 課税所得145万円以上 | 現役並み1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 4回目以降 44,400円 |
〇 | ||
| 一般(課税所得145万円未満) | 一般 | 18,000円(注4) | 57,600円 | 4回目以降 44,400円 |
× | |
| 低所得者2(注2) | 低2 | 8,000円 | 24,600円 | - | 〇 | |
| 低所得者1(注3) | 低1 | 8,000円 | 15,000円 | - | 〇 | |
(注1) 「課税所得」とは住民税課税所得金額のことで、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出される額です。
(注2) 住民税非課税世帯で、低所得1以外の方
(注3) 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
(ただし、公的年金収入が80万円を超える方が世帯にいる場合を除く)
(注4) 8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)は144,000円
- 4回目以降の限度額とは、過去12か月間で限度額まで達した回数が4回以上あった場合です(多数回該当)
問い合わせ(担当)
保健福祉部 保険年金課 資格年金係
電話番号:0225-95-1111 内線:2347
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当