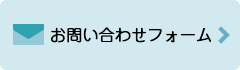ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種について
接種期限の延長について
令和7年3月31日を接種期限としておりましたHPVワクチンのキャッチアップ接種について、令和6年夏以降の大幅な需要増により、接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、条件付きで接種期限を1年間延長する方針について、国の審議会で了承されました。詳細は下記のとおりです。- 対象者
平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの女子
- 期限延長の条件
キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)に1回以上接種した方
(注意)令和4年3月31日までの接種歴がある方であっても、キャッチアップ接種期間の接種歴がない場合は、
期限延長の対象となりませんのでご注意ください。
- 延長後の接種期限
令和8年3月31日まで
子宮頸がんとは
子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の入口に近い部分にできるがんです。そのほとんどがHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因とされており、感染は主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。
9価ワクチン(シルガード9)の定期接種化について
令和5年4月1日から新たに9価ワクチン(シルガード9)が公費(無料)で接種できるようになりました。よって、公費(無料)で接種できるHPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類です。
HPVにはいくつかの種類(型)がありますが、9価ワクチン(シルガード9)は、このうち9種類のHPVの感染を防ぐワクチンです。その中でも、子宮頸がんの原因の80パーセントから90パーセントを占める、7種類のHPV(HPV16/18/31/33/45/52/58)の感染を予防することができます。
【9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について 厚生労働省ホームページ】外部サイトにリンクします
積極的な勧奨の再開について
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(HPVワクチン)は、平成25年4月に定期接種となった直後にワクチンとの因果関係が否定できない副反応が疑われる事例が多数発生したため、厚生労働省通知に基づき積極的な勧奨(対象者全員に対する予診票の個別送付など)を差し控えていました。その後、国の検討部会において、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められましたので、本市においても積極的な勧奨が再開されました。
また、積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方を対象に、時限的に将来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う「キャッチアップ接種(過去に合計3回接種していない方)」を実施しています。接種を希望する方は、厚生労働省ホームページ及び厚生労働省ホームページ内リーフレットをよくご覧いただき、ワクチン接種の有効性および安全性について、十分に理解いただいた上で、接種を受けてください。
【ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ キャッチアップ接種のご案内 厚生労働省ホームページ】外部サイトにリンクします
対象者
接種時点で石巻市に住民登録のある女子(標準的な接種時期は中学1年生です)
| 学年と年齢 | 生年月日 | |
| 通常接種 | 小学校6年生(12歳)から高校1年生(16歳) | 平成21年4月2日から平成26年4月1日まで |
| キャッチアップ接種 | 高校2年生(17歳)から28歳 | 平成9年4月2日から平成21年4月1日まで |
令和7年4月下旬に、平成24年4月2日から平成25年4月1日までに生まれた女子に対して予診票を送付します。
平成21年4月2日生まれから平成22年4月1日生まれの方は、令和8年3月31日が接種期限です。
接種は合計3回ですが、最短4か月で完了することもできます。
11月までに1回目の接種をすれば、令和8年3月までに3回の接種を完了することが可能です。
接種期限
1 通常接種の場合は、高校1年生(16歳)の年度末まで
2 キャッチアップ接種期間に1回以上接種をしている場合は、令和8年3月31日までとする。
接種費用
接種期限内に規定の回数と間隔で接種する場合は、無料で接種できます。
接種期限を過ぎると全額自己負担となりますので、ご注意ください。
HPVワクチンについて
接種回数と標準的な接種間隔
| ワクチンの種類 | 接種回数 | 標準的な接種間隔 |
| 2価ワクチン (サーバリックス) |
3回 |
1回目の接種から1か月の間隔をおいて2回目を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を行う。 |
| 4価ワクチン (ガーダシル) |
3回 |
1回目の接種から2か月の間隔をおいて2回目を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を行う。 |
| 9価ワクチン (シルガード9) |
2回または3回 | 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合の接種回数は2回となり、1回目の接種から6か月の間隔をおいて2回目を行う。 1回目の接種を15歳になってから受ける場合の接種回数は3回となり、1回目の接種から2か月の間隔をおいて2回目を行った後、 1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を行う。 |
原則、1回目から3回目まで同じワクチンを使用します。
過去に接種歴がある場合、原則、同じワクチンで残りの回数を接種することとなりますが、接種したワクチンの種類が不明の場合は、医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。
この場合、結果として異なる種類のワクチンが接種される可能性がありますので、ワクチンの互換性に関する安全性、免疫原性及び有効性についても、十分な説明を受けてください。
指定医療機関
令和7年度指定医療機関一覧
上記医療機関のほか、宮城県広域化予防接種事業(外部サイトにリンクします)の実施医療機関でも接種することができます。変更となる場合もありますので、事前に医療機関へ問い合わせてください。
なお、特別な事情により、県内の指定医療機関以外または県外の医療機関での接種を希望する場合は、「予防接種実施依頼書」が必要になりますので、接種の10日前までに健康推進課へご連絡ください。
(「予防接種実施依頼書」とは、受けた予防接種により健康被害が生じた場合に、石巻市が健康被害救済のための措置を講じることを明らかにする書類です。)
副反応等について
接種後に気になる症状があるときは、まずは接種医療機関にご相談ください。
副反応の詳細については、厚生労働省ホームページ及び厚生労働省ホームページ内リーフレットをご覧ください。
【ヒトパピローマウイルス感染症 子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン 厚生労働省ホームページ】外部サイトにリンクします
健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、なくすことができないものであるため、治療が必要となったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合の救済制度が設けられています。
リーフレット(健康被害救済制度)(外部サイトにリンクします)もご確認ください。
子宮がん検診について
予防接種ですべての子宮がんを予防できるわけではありません。
HPVワクチンを受けた場合であっても、免疫が不十分である場合やワクチンに含まれる型以外の型により子宮頸がんの可能性がありますので、20歳を過ぎたら定期的に子宮がん検診を受けることが大切です。
HPV自主検査について
石巻市では、自宅でできる子宮頸がんのリスク検査(HPV自主検査)を実施しています。
対象の方には個別で通知しています。詳しくは「石巻市子宮頸がん検診推進(HPV自主検査)事業のお知らせ」をご覧ください。
関連ファイル
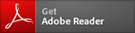 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。
関連リンク
- ヒトパピローマウイルス感染症-子宮頸がんとHPVワクチン-(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)について(宮城県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111
予防接種・健診担当
地域医療・総務担当
歯科保健担当
母子保健(乳幼児健診)担当
精神保健担当
成人保健担当
栄養担当